
プロフィール

自らのクルマのカスタムにつぎ込んだ金額は4桁万円に迫るほどというコアなカスタム中毒者でありジャンキーな経歴の持ち主。現在ラリー屋。好きな車はBNR32.最高自動車同時保有台数5。「公道はサーキットではない」をモットーに安全運転を第一とするゴールド免許ドライバー。
カテゴリ
最近の記事
NV350の取材先を募集中です! (7/16)
コラボ企画を募集中です (6/4)
サイト「フルモデルチェンジ」のお知らせ (5/24)
オートメモリーさんが「俺たちに任せろMAPに」! (4/26)
俺たちに任せろマップ登録ショップさんのお知らせ (3/10)
神戸市中央区「Schott KOBE」さんセール中! (2/26)
「俺たちに任せろマップ」登録ショップさん増加中! (2/19)
カスタムインフェクションを改めてご紹介 (2/5)
過去記事
最近のコメント
ハーレー / NewOrderChopperShow in KOBE・・・
お気に入り
ブログ内検索
QRコード
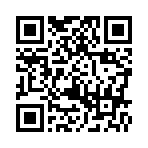
アクセスカウンタ
読者登録
自動車内装に見る人工皮革、合成皮革
2011年08月20日
『クルマ・バイクの内装・カスタム病に感染したジャンキーの集まるサイト』と銘打っているカスタムインフェクションとしては、内装の事についての考え方もブレてはいけないと思っています。

車輛内装材とは言うものの、「内装・DIY」コーナーで、特に座席シート部分の素材にスポットを当ててニュース配信をしています。MJの部屋ではまず「自動車シート素材」について考えてみましょう。
自動車にはグレード別にいわゆる塩ビ素材(商用車・トラックに多い)ファブリック素材(標準的な乗用車に多い)、合成皮革素材(本革の代用として防水性などを持った機能性が求められる多目的車に多い)、人工皮革素材(シートに付加価値や軽量化、スポーツ性などに重点を置く車種に多い)、そして本革素材(言わずと知れた高級車に採用)大きく分けてこの5種類に分けられています。
塩ビ素材はある時期には環境ホルモンであるダイオキシンを発生するという報道でバッシングを受け、大きなダメージを受けました。しかしその後の報道で、廃棄時の処理方法を正しく行うことで、そのような有毒なガスは発生しないことが立証されています。現在、塩ビはその実用性の高さが認められさまざまな製品に使用されており、最近では「エコビ」と呼ばれる地球環境に配慮した素材も開発されるほどです。
確かに塩ビほど完成された人工的な素材はないと言っても過言ではありません。価格が安いうえ耐久性や耐候性、耐薬性などの機能から活躍の場は幅広い。自動車、特に商用車やトラックへの採用が多いのはとりわけこの耐久性と耐候性を買われての事です。その後この優等生「塩ビ」に代わって登場したのが合成皮革。合成皮革も同じく石油を原料としているのですが、塩ビのように薄っぺらく、ビニール特有の固さを出来るだけ抑え、より本革に近い、風合いの高いものに近づけることに成功した素材なのです。製法その他については後日にでも書くこととして、合成皮革はこのような経緯で生まれたのです。
次に人工皮革。この素材は合成皮革とよく混同されるのですが、両者の大きな違いは使われる基布。その違いは人工皮革、合成皮革ともベースとなる基布に発泡させたポリウレタンを含浸するのですが、人工皮革はこのベース(基布)がマイクロファイバー製の基布を使用している点にあります。マイクロファイバーは超極細繊維と表現される3次元絡構造をしています。マイクロファイバーとレギュラーファイバーについても別記しますが、超極細繊維化することで、より耐久性の高い、風合いの良い素材を作り出すことができるのです。

最近は人工皮革に使用される有機溶剤を極力減らそうと、「エコフレンドリー」を謳った地球環境にやさしい素材の開発に大手メーカーが相次いで取り組んでおられます。エコカーと言えば「燃費のイイ車」というイメージが先行しますが、リサイクルや使用している原料もエコを主張する時代も遠くないと思われます。
自動車のシート材としては依然として「本革シート」が最高級品とされています。ドアを開けて室内に入った瞬間のあの独特の香りや、着座時の感触のファンも多いようです。そんなファンの「本革」へこだわりは留まるところを知らず、室内を「自分だけのくつろげる特別な空間として極めたい」と考える方も多くなりました。そんな声にこたえる形で、自動車各社側も相次いで「本革」という素材をただ使用するだけでなく、タンナーにもこだわりはじめ、有名な英国のコノリー社の「コノリーレザー」のようなが名だたる高級車の内装材に採用されるようになりました。さすがにこのレベルまでの人工皮革の開発には至っていませんが、逆にその「超軽量」という特性を活かし、モータースポーツの世界では本革を押しのけて採用されています。
ということでやっと人工皮革と合成皮革はいかに自動車内装材への採用が重要で有用かというお話の前提の大部分がここでお話しできたわけです。
興味のない方は長文でお疲れのことでしょう。しかし、まだまだ続きます。
本コラムで申し上げたい話はここからなのです。
これだけの前提と、人工皮革合成皮革の経緯をお話ししながらお伝えしたいのは自動車メーカーの方々は、「人工皮革と合成皮革の線引きをあまり重要視されていない」という現実です。
細かい棲み分けはあまりユーザーにとっては重要なことではないのかもしれませんが、両者は似て非なるもの。注がれている技術や開発段階での素材の性格は全く違います。しかも、一般ユーザーの受ける「合成皮革」のイメージは「合皮」であり、「安物」というイメージがまだついて回っています。
しかし、町に出回っている安価なバッグに使用されている合成皮革と自動車内装材に採用されるレベルの「合成皮革」は雲泥の差があり、自動車内装材として採用されるには相当高いスペックが要求されるのです。耐久性はもちろん、夏場など室内温度が上昇し70℃に達することもあり、逆に冬場は氷点下になることもあります。そんな耐候性も求められ、さらに過酷な環境に置かれた場合でも有害物質を発生しないというような性能や色落ち、耐摩耗性などが求められます。某シート素材メーカーの担当者の話をお聞きするとギャランティ(製品保証)期間は15年を要求されることもあるそうです。
先ほどお話した一般的な「合皮製バッグ」や「合皮製ジャケット」は長く持っても正直2、3年だろうと思います。合成皮革には最大の弱点である加水分解という化学反応が否応なしに起こるからです。この耐久性に関しても使用される表面処理剤や薬品によって大きな差が出るため、つまりそれらが「製品の価格差」に表れているのです。
長くなりましたが、これだけ高いレベルの素材が自動車をはじめ二輪車にも採用されているのです。
しかし、メーカーのカタログ1つとっても主要装備一覧表の欄外、注釈部分に「※シートの一部に合成皮革を使用しています」と書かれているだけ…。もったいないです。
確かに消費者にとっては、合成皮革と書く方が人工皮革と書くよりも馴染みがあるのかもしれない。でもやっぱり人工皮革なのに「合成皮革を使用してます」って表記するのはおかしい。この逆もしかり。
どうしてなんだろうといつも思っていました。
「このクルマ、大体月2,000台は売れるから、メートル当たり○○円でいれてね」という会話がされているのかどうか分かりません。「安く入れる代わりにうちの製品、ちゃんとカタログで紹介してよね」って一言言えないんだろうか…。恐らく言ってるんだろうなぁ…。素材メーカーも自動車メーカーにお願いしているのだと思いますが、発注者と受注者という力関係からからその「お願い」が進んでいないように思います。
言いにくいなら“まだ”損得勘定のない外部の私がこういう形でご紹介するしかないなと考えました。
普段から実はMJはこんなことも考えながら内装からもクルマ、バイク業界を明るくしたいと日々真剣に考えています。

車輛内装材とは言うものの、「内装・DIY」コーナーで、特に座席シート部分の素材にスポットを当ててニュース配信をしています。MJの部屋ではまず「自動車シート素材」について考えてみましょう。
自動車にはグレード別にいわゆる塩ビ素材(商用車・トラックに多い)ファブリック素材(標準的な乗用車に多い)、合成皮革素材(本革の代用として防水性などを持った機能性が求められる多目的車に多い)、人工皮革素材(シートに付加価値や軽量化、スポーツ性などに重点を置く車種に多い)、そして本革素材(言わずと知れた高級車に採用)大きく分けてこの5種類に分けられています。
塩ビ素材はある時期には環境ホルモンであるダイオキシンを発生するという報道でバッシングを受け、大きなダメージを受けました。しかしその後の報道で、廃棄時の処理方法を正しく行うことで、そのような有毒なガスは発生しないことが立証されています。現在、塩ビはその実用性の高さが認められさまざまな製品に使用されており、最近では「エコビ」と呼ばれる地球環境に配慮した素材も開発されるほどです。
確かに塩ビほど完成された人工的な素材はないと言っても過言ではありません。価格が安いうえ耐久性や耐候性、耐薬性などの機能から活躍の場は幅広い。自動車、特に商用車やトラックへの採用が多いのはとりわけこの耐久性と耐候性を買われての事です。その後この優等生「塩ビ」に代わって登場したのが合成皮革。合成皮革も同じく石油を原料としているのですが、塩ビのように薄っぺらく、ビニール特有の固さを出来るだけ抑え、より本革に近い、風合いの高いものに近づけることに成功した素材なのです。製法その他については後日にでも書くこととして、合成皮革はこのような経緯で生まれたのです。
次に人工皮革。この素材は合成皮革とよく混同されるのですが、両者の大きな違いは使われる基布。その違いは人工皮革、合成皮革ともベースとなる基布に発泡させたポリウレタンを含浸するのですが、人工皮革はこのベース(基布)がマイクロファイバー製の基布を使用している点にあります。マイクロファイバーは超極細繊維と表現される3次元絡構造をしています。マイクロファイバーとレギュラーファイバーについても別記しますが、超極細繊維化することで、より耐久性の高い、風合いの良い素材を作り出すことができるのです。

最近は人工皮革に使用される有機溶剤を極力減らそうと、「エコフレンドリー」を謳った地球環境にやさしい素材の開発に大手メーカーが相次いで取り組んでおられます。エコカーと言えば「燃費のイイ車」というイメージが先行しますが、リサイクルや使用している原料もエコを主張する時代も遠くないと思われます。
自動車のシート材としては依然として「本革シート」が最高級品とされています。ドアを開けて室内に入った瞬間のあの独特の香りや、着座時の感触のファンも多いようです。そんなファンの「本革」へこだわりは留まるところを知らず、室内を「自分だけのくつろげる特別な空間として極めたい」と考える方も多くなりました。そんな声にこたえる形で、自動車各社側も相次いで「本革」という素材をただ使用するだけでなく、タンナーにもこだわりはじめ、有名な英国のコノリー社の「コノリーレザー」のようなが名だたる高級車の内装材に採用されるようになりました。さすがにこのレベルまでの人工皮革の開発には至っていませんが、逆にその「超軽量」という特性を活かし、モータースポーツの世界では本革を押しのけて採用されています。
ということでやっと人工皮革と合成皮革はいかに自動車内装材への採用が重要で有用かというお話の前提の大部分がここでお話しできたわけです。
興味のない方は長文でお疲れのことでしょう。しかし、まだまだ続きます。
本コラムで申し上げたい話はここからなのです。
これだけの前提と、人工皮革合成皮革の経緯をお話ししながらお伝えしたいのは自動車メーカーの方々は、「人工皮革と合成皮革の線引きをあまり重要視されていない」という現実です。
細かい棲み分けはあまりユーザーにとっては重要なことではないのかもしれませんが、両者は似て非なるもの。注がれている技術や開発段階での素材の性格は全く違います。しかも、一般ユーザーの受ける「合成皮革」のイメージは「合皮」であり、「安物」というイメージがまだついて回っています。
しかし、町に出回っている安価なバッグに使用されている合成皮革と自動車内装材に採用されるレベルの「合成皮革」は雲泥の差があり、自動車内装材として採用されるには相当高いスペックが要求されるのです。耐久性はもちろん、夏場など室内温度が上昇し70℃に達することもあり、逆に冬場は氷点下になることもあります。そんな耐候性も求められ、さらに過酷な環境に置かれた場合でも有害物質を発生しないというような性能や色落ち、耐摩耗性などが求められます。某シート素材メーカーの担当者の話をお聞きするとギャランティ(製品保証)期間は15年を要求されることもあるそうです。
先ほどお話した一般的な「合皮製バッグ」や「合皮製ジャケット」は長く持っても正直2、3年だろうと思います。合成皮革には最大の弱点である加水分解という化学反応が否応なしに起こるからです。この耐久性に関しても使用される表面処理剤や薬品によって大きな差が出るため、つまりそれらが「製品の価格差」に表れているのです。
長くなりましたが、これだけ高いレベルの素材が自動車をはじめ二輪車にも採用されているのです。
しかし、メーカーのカタログ1つとっても主要装備一覧表の欄外、注釈部分に「※シートの一部に合成皮革を使用しています」と書かれているだけ…。もったいないです。
確かに消費者にとっては、合成皮革と書く方が人工皮革と書くよりも馴染みがあるのかもしれない。でもやっぱり人工皮革なのに「合成皮革を使用してます」って表記するのはおかしい。この逆もしかり。
どうしてなんだろうといつも思っていました。
「このクルマ、大体月2,000台は売れるから、メートル当たり○○円でいれてね」という会話がされているのかどうか分かりません。「安く入れる代わりにうちの製品、ちゃんとカタログで紹介してよね」って一言言えないんだろうか…。恐らく言ってるんだろうなぁ…。素材メーカーも自動車メーカーにお願いしているのだと思いますが、発注者と受注者という力関係からからその「お願い」が進んでいないように思います。
言いにくいなら“まだ”損得勘定のない外部の私がこういう形でご紹介するしかないなと考えました。
普段から実はMJはこんなことも考えながら内装からもクルマ、バイク業界を明るくしたいと日々真剣に考えています。
エコカー事情観察
2011年08月08日
先日MAZDAの新型デミオに試乗した。新型のデミオが出たのはずいぶん前の事。目的は搭載された新世代ガソリンエンジン「SKYACTIV」だ。普段はカスタムされたクルマや、ドレスアップされたクルマばかり見てきているだけに、こういう時は改めて「ノーマル」のクルマの良さを実感したりする。大きな自動車メーカーが莫大な開発費用をかけて開発するのだから、妥協を許さない納得の1台が生まれているはず。そんな期待をして「SKYACTIV」に臨んだ。
前回の東京モーターショーで初めてお目見えした「SKYACTIV」エンジン。当時はエコカーブームの初期のころで、三菱自動車が電気軽自動車「i-MIEV」を発表。日産自動車がいよいよ市販ベースになった電気自動車「LEAF」を展示。また、トヨタのプリウスが発売された直後でもあり、プリウスはプラグインハイブリッドモデルが公開されているというまるで「エコカー・モーターショー」状態だった。ちょうどリーマンショック、世界同時不況など世界的な金融危機に陥っている中でのモーターショー開催だったため、軒並み海外勢は出展を差し控えていた寂しいモーターショーだったと記憶している。
当時雑誌記者として「東京モーターショー2009」を取材したが、一番の注目を浴びたのがトヨタの「FT-86」。トヨタの名車ハチロクの再来と言われたコンパクトFRスポーツの復活と騒がれ、記者は軒並みトヨタブースへ集まっていた。若者のスポーツカー離れのニュースは当時から流れていたし、スポーツカーも電気自動車になるなどと色々な憶測も飛び交った。しかしその後実際にアメリカのテスラ社が電気スーパースポーツカーを出したのだが。

「マツダのコンセプトカー清(きよら)」
そんな中で私の目を一際目を引いたのがMAZDAのブースだった。当時「清(きよら)」という名前のコンセプトカーでショーに登場していたスカイアクティブエンジンを搭載したクルマでした。「ガソリンエンジンで燃費リッターあたり32.0Km/L」確か当時そんなフレコミでした。国産各社がエコカーとして当時出展したのは上記のとおりハイブリッドかEV(電気自動車)。そんな中でMAZDAはガソリンエンジンの燃焼効率から内燃機関を徹底的に見直したガソリンエンジンで対向してきたことに感動した。
その頃から気になっていた、SKYACTIV。「燃費30.0km/lは本当なのか」、実力はどうなのかと期待を膨らませての試乗。トヨタプリウス、日産リーフ、ホンダインサイト、マツダデミオ。それぞれエコカーと言える低燃費。日本を代表するエコカーに試乗したが、それぞれ一長一短がある。。電気自動車を誰が究極のエコカーと決めたのか。Co2を出さないだけがエコなのか?ハイブリッドだったら燃費がいいのか?電気自動車は充電のインフラの問題が山積。ハイブリッド車は燃料電池の希少金属、レアアースの問題もある。どれも完ぺきではないのである。逆にそれでいいのだと思う。各メーカーが自信を持って出した究極と思えるエコカー、ライバルたちはそれらを徹底して研究し、さらに高い技術を持ったエコカーを生み出してゆく。それに消費者は自分なりのライフスタイルに合わせてエコカーを購入すればいいと思う。
変な話、土曜日曜日しか車に乗らないAさんは普段電車移動。毎日通勤にくるまを使用するBさんは休みの日も車に乗る。この場合Aさんはわざわざエコカーに乗る必要があるだろうか?Bさんと比べるとはるかに排気ガスの排出量は少ないはずである。Aさんがエコカーにするよりも、Bさんが普段乗っているクルマをエコカーにする方がよっぽどエコ。エコカーにするべきは普通乗用車ではなく商用車だと私は常々思っている。確かに天然ガス自動車や水素ガス自動車も開発されている。実用的な部分ではまだまだ一般化されていない。そういった意味からも既存のガソリンエンジンを進化させたMAZDAの技術は当時から素晴らしいと感じていた。そのため今回のSKYACTIV搭載のデミオに乗ってみたかったのである。
「エコカー」モーターショーが奏功したのか、その後2年間で続々と欧州メーカーが低燃費エンジンを開発してきた。VWの「TSIエンジン」、メルセデスのディーゼルエンジン「ブルーテック」。フィアットの「ツインエア」などがその代表格である。いまやあのポルシェやフェラーリまでもハイブリッドスポーツカーを開発している。ランボルギーニのように「うちのクルマの世界的な生産台数は環境に影響を与えるほどの数ではない」、「ハイブリッドにすることはランボルギーニがランボルギーニである事を否定するのと同じだ」という強気なメーカーもある。これは逆に潔くていいと思う。国が違えば自動車事情も違うが、低燃費、低公害社会は地球規模の願いだ。その思いは全世界共通。開発のベクトルは同じはず、アプローチの方法はたくさんあればあるほどいい。答えはまだまだ出なくていいのだ。
まだまだエコカー開発競争は始まったばかり。国内外の各自動車メーカーに期待したい。まだまだ日本も世界と戦える。優秀なメカニックを抱えるモノづくり大国日本。頑張ってほしいと思う。
前回の東京モーターショーで初めてお目見えした「SKYACTIV」エンジン。当時はエコカーブームの初期のころで、三菱自動車が電気軽自動車「i-MIEV」を発表。日産自動車がいよいよ市販ベースになった電気自動車「LEAF」を展示。また、トヨタのプリウスが発売された直後でもあり、プリウスはプラグインハイブリッドモデルが公開されているというまるで「エコカー・モーターショー」状態だった。ちょうどリーマンショック、世界同時不況など世界的な金融危機に陥っている中でのモーターショー開催だったため、軒並み海外勢は出展を差し控えていた寂しいモーターショーだったと記憶している。
当時雑誌記者として「東京モーターショー2009」を取材したが、一番の注目を浴びたのがトヨタの「FT-86」。トヨタの名車ハチロクの再来と言われたコンパクトFRスポーツの復活と騒がれ、記者は軒並みトヨタブースへ集まっていた。若者のスポーツカー離れのニュースは当時から流れていたし、スポーツカーも電気自動車になるなどと色々な憶測も飛び交った。しかしその後実際にアメリカのテスラ社が電気スーパースポーツカーを出したのだが。

「マツダのコンセプトカー清(きよら)」
そんな中で私の目を一際目を引いたのがMAZDAのブースだった。当時「清(きよら)」という名前のコンセプトカーでショーに登場していたスカイアクティブエンジンを搭載したクルマでした。「ガソリンエンジンで燃費リッターあたり32.0Km/L」確か当時そんなフレコミでした。国産各社がエコカーとして当時出展したのは上記のとおりハイブリッドかEV(電気自動車)。そんな中でMAZDAはガソリンエンジンの燃焼効率から内燃機関を徹底的に見直したガソリンエンジンで対向してきたことに感動した。
その頃から気になっていた、SKYACTIV。「燃費30.0km/lは本当なのか」、実力はどうなのかと期待を膨らませての試乗。トヨタプリウス、日産リーフ、ホンダインサイト、マツダデミオ。それぞれエコカーと言える低燃費。日本を代表するエコカーに試乗したが、それぞれ一長一短がある。。電気自動車を誰が究極のエコカーと決めたのか。Co2を出さないだけがエコなのか?ハイブリッドだったら燃費がいいのか?電気自動車は充電のインフラの問題が山積。ハイブリッド車は燃料電池の希少金属、レアアースの問題もある。どれも完ぺきではないのである。逆にそれでいいのだと思う。各メーカーが自信を持って出した究極と思えるエコカー、ライバルたちはそれらを徹底して研究し、さらに高い技術を持ったエコカーを生み出してゆく。それに消費者は自分なりのライフスタイルに合わせてエコカーを購入すればいいと思う。
変な話、土曜日曜日しか車に乗らないAさんは普段電車移動。毎日通勤にくるまを使用するBさんは休みの日も車に乗る。この場合Aさんはわざわざエコカーに乗る必要があるだろうか?Bさんと比べるとはるかに排気ガスの排出量は少ないはずである。Aさんがエコカーにするよりも、Bさんが普段乗っているクルマをエコカーにする方がよっぽどエコ。エコカーにするべきは普通乗用車ではなく商用車だと私は常々思っている。確かに天然ガス自動車や水素ガス自動車も開発されている。実用的な部分ではまだまだ一般化されていない。そういった意味からも既存のガソリンエンジンを進化させたMAZDAの技術は当時から素晴らしいと感じていた。そのため今回のSKYACTIV搭載のデミオに乗ってみたかったのである。
「エコカー」モーターショーが奏功したのか、その後2年間で続々と欧州メーカーが低燃費エンジンを開発してきた。VWの「TSIエンジン」、メルセデスのディーゼルエンジン「ブルーテック」。フィアットの「ツインエア」などがその代表格である。いまやあのポルシェやフェラーリまでもハイブリッドスポーツカーを開発している。ランボルギーニのように「うちのクルマの世界的な生産台数は環境に影響を与えるほどの数ではない」、「ハイブリッドにすることはランボルギーニがランボルギーニである事を否定するのと同じだ」という強気なメーカーもある。これは逆に潔くていいと思う。国が違えば自動車事情も違うが、低燃費、低公害社会は地球規模の願いだ。その思いは全世界共通。開発のベクトルは同じはず、アプローチの方法はたくさんあればあるほどいい。答えはまだまだ出なくていいのだ。
まだまだエコカー開発競争は始まったばかり。国内外の各自動車メーカーに期待したい。まだまだ日本も世界と戦える。優秀なメカニックを抱えるモノづくり大国日本。頑張ってほしいと思う。
モト・コムさんで聞いたカスタム事情
2011年08月02日
先日「MJ lab」の方でご紹介した「モト・コム」さんで色々とお話を伺っていたところ興味深い話があったので、「認定ショップ」とは別でご紹介したいと思います。

最近のカスタム事情、と大きなタイトルを掲げたものの、そんな大勢を図るようなマネは私にはできませんが、気軽な話としてまとめます。前篇でも書いた通り、なかなか若い世代(だいたい免許取得~20代後半)がカスタムに興味がないと嘆いておられます。興味の対象が変わったのか、別にバイクを必要とする若者が減り、さらにこの少子化がバイク離れに拍車を掛けているようです。自動車業界にも同じことが言えるのですが…。
長引く不況から「バイクを買える」、すなわち購入できるだけの一定の収入を持っている人が少なくなったということも背景にあるようです。ローンで無理して買おうとしても定職に就いていないから「毎月決まった収入が無い=信用担保力に欠ける」と世間では判断されてしまうのです。購買意欲はあるけれども、購買能力が無い。欲しいという気持ちはあるけど、購入するという行動に移れない?そんな事情も少なからずあると思います。
当たり前のことを書いているようですが、どこのお店に行ってもこのようなお話は少なからずお聞きしているのです…。

新車が売れないと中古車も出てこない。これは当たり前です。テレビで「中古バイクを待ってる人が大勢います」というような表現で中古車販売を宣伝している会社のCMを見ました。不況だからここは中古で我慢しよう…。という考えから出費を抑える意味で皆さん中古車を購入されます。そんな考えの人が増えたからこんなCMも生まれたように思います。実際に某バイクメーカーの新車販売代理店の方にお聞きすると「新車販売台数は減少傾向」、「明確に数字で出ている」との回答…。
買い控え、不要不急の物は買わない。まさにバイクやクルマはこれに当てはまってしまうんです。突然ですが皆さん、不況と言われ続けてどれくらい経つと思いますか?諸説ありますが、不況と言われ始めて約20年経過しているそうです。このような経済状況にもう20年も慣らされていると思うとぞっとします。
バイクカスタムの話に戻ると、昔は原チャリからネイキッドタイプのバイクへ、そして国産アメリカン、やがて憧れのハーレーを購入する。という方程式が当たり前のように繰り返されていたそうです。しかしその神話は脆くも崩れ、今は免許取得後、スクーター購入→ビックスクーターに。という構図になりつつあるそうです。本来それぞれの段階で当然カスタムなり買い替えなりが発生していた。つまりいろんな段階でお金が発生し、業界の中を回っていたということです。スクーターが流行るのはその手軽さとカスタムパーツの多さから。しかしそこからハーレーなどのいわゆるクラッチ付きには戻ってこないようです。
それが今や「カスタムって?」という人も増えているようで、こんなサイトを運営している立場からすると恐ろしい話ですが…。最近のカスタム事情を総括する意味では、情報の多様化も大きな影響があるようです。
雑誌やネットの普及で色々な情報が自在に手に入るため個性が加速し自分らしさの表現が多様化しました。それに合わせてバイク業界のカスタムも進化し、様々なパーツも開発されカスタムも容易になっています。情報が溢れているだけに価格競争も激しくなりカスタムショップの利益を圧迫していることも事実、逆に売り上げの一助となっていることも事実。現実はこのような事情のようです。

「モト・コム」さんでお聞きした最近の若い人のお店での行動。記事にも書きましたが、話を全くしないそうです。PCと向き合う時間が増えたせいか、友達が少ないのか。
値引き交渉なんかもってのほか、何が欲しいかすら意思表示をうまくできない若い人、増えているそうです。「このマフラー欲しいねんけど、予算的に厳しいから負けてくれんかなー」とか、「結構前からあのパーツおいてあるからちょっと安くしてくれへん?」とかコミュニケーションを取らないから損しているそうです。確かにお客さんと店主という立場はありますが、同じバイク愛好家としていろんな話をしたいと思っているそうです。「何でも相談に乗ってくれるバイク屋のおっちゃん」がいる「町のバイク屋」的な存在のお店はまだまだたくさんあると思っています。
こんなことを考えながら今日もどこかでMJが取材中です。取材依頼お待ちしています。
詳しくはこちらから→http://mjlab.ko-co.jp/e164166.html
最近のカスタム事情、と大きなタイトルを掲げたものの、そんな大勢を図るようなマネは私にはできませんが、気軽な話としてまとめます。前篇でも書いた通り、なかなか若い世代(だいたい免許取得~20代後半)がカスタムに興味がないと嘆いておられます。興味の対象が変わったのか、別にバイクを必要とする若者が減り、さらにこの少子化がバイク離れに拍車を掛けているようです。自動車業界にも同じことが言えるのですが…。
長引く不況から「バイクを買える」、すなわち購入できるだけの一定の収入を持っている人が少なくなったということも背景にあるようです。ローンで無理して買おうとしても定職に就いていないから「毎月決まった収入が無い=信用担保力に欠ける」と世間では判断されてしまうのです。購買意欲はあるけれども、購買能力が無い。欲しいという気持ちはあるけど、購入するという行動に移れない?そんな事情も少なからずあると思います。
当たり前のことを書いているようですが、どこのお店に行ってもこのようなお話は少なからずお聞きしているのです…。
新車が売れないと中古車も出てこない。これは当たり前です。テレビで「中古バイクを待ってる人が大勢います」というような表現で中古車販売を宣伝している会社のCMを見ました。不況だからここは中古で我慢しよう…。という考えから出費を抑える意味で皆さん中古車を購入されます。そんな考えの人が増えたからこんなCMも生まれたように思います。実際に某バイクメーカーの新車販売代理店の方にお聞きすると「新車販売台数は減少傾向」、「明確に数字で出ている」との回答…。
買い控え、不要不急の物は買わない。まさにバイクやクルマはこれに当てはまってしまうんです。突然ですが皆さん、不況と言われ続けてどれくらい経つと思いますか?諸説ありますが、不況と言われ始めて約20年経過しているそうです。このような経済状況にもう20年も慣らされていると思うとぞっとします。
バイクカスタムの話に戻ると、昔は原チャリからネイキッドタイプのバイクへ、そして国産アメリカン、やがて憧れのハーレーを購入する。という方程式が当たり前のように繰り返されていたそうです。しかしその神話は脆くも崩れ、今は免許取得後、スクーター購入→ビックスクーターに。という構図になりつつあるそうです。本来それぞれの段階で当然カスタムなり買い替えなりが発生していた。つまりいろんな段階でお金が発生し、業界の中を回っていたということです。スクーターが流行るのはその手軽さとカスタムパーツの多さから。しかしそこからハーレーなどのいわゆるクラッチ付きには戻ってこないようです。
それが今や「カスタムって?」という人も増えているようで、こんなサイトを運営している立場からすると恐ろしい話ですが…。最近のカスタム事情を総括する意味では、情報の多様化も大きな影響があるようです。
雑誌やネットの普及で色々な情報が自在に手に入るため個性が加速し自分らしさの表現が多様化しました。それに合わせてバイク業界のカスタムも進化し、様々なパーツも開発されカスタムも容易になっています。情報が溢れているだけに価格競争も激しくなりカスタムショップの利益を圧迫していることも事実、逆に売り上げの一助となっていることも事実。現実はこのような事情のようです。
「モト・コム」さんでお聞きした最近の若い人のお店での行動。記事にも書きましたが、話を全くしないそうです。PCと向き合う時間が増えたせいか、友達が少ないのか。
値引き交渉なんかもってのほか、何が欲しいかすら意思表示をうまくできない若い人、増えているそうです。「このマフラー欲しいねんけど、予算的に厳しいから負けてくれんかなー」とか、「結構前からあのパーツおいてあるからちょっと安くしてくれへん?」とかコミュニケーションを取らないから損しているそうです。確かにお客さんと店主という立場はありますが、同じバイク愛好家としていろんな話をしたいと思っているそうです。「何でも相談に乗ってくれるバイク屋のおっちゃん」がいる「町のバイク屋」的な存在のお店はまだまだたくさんあると思っています。
こんなことを考えながら今日もどこかでMJが取材中です。取材依頼お待ちしています。
詳しくはこちらから→http://mjlab.ko-co.jp/e164166.html










